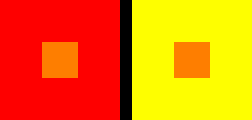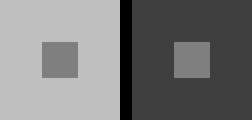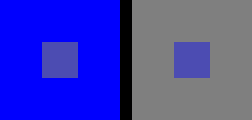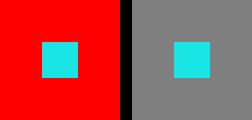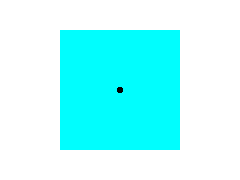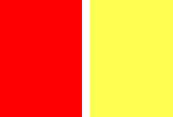色の対比
対比(Color contrast)とはある色が周囲の他の色の影響を受け、単独で見る時とは違って見える現象を言います。
従って、皆さんがパレット上で入念に用意した色ミックスも、実際に使用した場合にはその回りの色に影響を受けて
意図していた効果が得られない場合もよくあります。 絵の中の一つづつのアイテムをパレットで前もって用意した
絵の具で描くのと、絵全体の中の一つのアイテムを全体の一部としてその都度に色の調和をとりながら描くのとでは
陶然結果は違う場合があるでしょう。 アイテムを描くのではなく構図を描くと言う表現はこんな所にあるんでしょう。
色の対比には大きく分けて「空間的に接する」同時対比と「時間的に接する」継続対比があります。
A. 同時対比 (Simultaneous contrast)
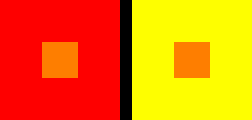 |
(1) 色相によるコントラスト
色相の異なる2色は互いに影響しあって、その2色間の色相差がより大きく強調されて見えます。 つまり色相はそれぞれ色相環状の反対の方向へ移ったように感じられます。 左例のオレンジ色は赤の中にある場合は黄色がかって見え、黄色の中の場合は赤がかって見えます。 |
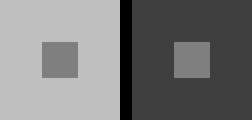 |
(2) 明度によるコントラスト
明度の異なる2色は互いに影響しあって、明るい色はより明るく、暗い色はより暗く感じられます。
左例の左右の同じ明度のグレーが左は暗く、右は明るく感じられます。
その他の例
|
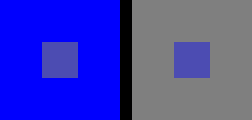 |
(3) 彩度によるコントラスト
彩度の異なる2色は互いに影響しあって、彩度の高い色はより鮮やかに、低い方の色はより濁って見えます。 左例の左右の中心の青はそれぞれ同じ彩度ですが、左の彩度が高い青の中では実際よりも少し濁って、右の彩度が低いグレーの中では実際よりも少し鮮やかに見ます。従って左右の中心の青は右の方が鮮やかに見えます。 |
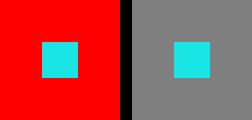 |
(4) 補色によるコントラスト
補色関係の2色は互いに影響しあってそれぞれの彩度が高まって見えます。 純色同士の場合には著しく、特に左の赤とシアンの純色の様に補色で明度の等しい場合はギラギラと強烈な対比現象が現れます。
その他の例
|
|
(5) 寒暖によるコントラスト |
|
(6) 面積によるコントラスト
同じ色でも面積が大きいほど明度が高くなって見えることがあります。これが面積効果(面積対比)です。
インテリアのお店で小さいカラーサンプルを見て色を決めても、実際に壁紙にするとサンプルと違って見えたりします。 |
 |
(7)縁辺対比
明度対比を応用した現象です。明るい色と接している部分は暗く見え、逆に暗い部分に接している部分は 明るく見えます。 |
B. 継続対比 (Successive contrast)
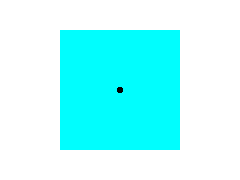 |
継続対比とはある色を一定時間以上見つめた後に、他の色を見る時に前に見つめた色が後の色に影響を与えて色が違って見える対比錯視現象を言います。
有彩色の場合には心理補色現象が作用して始めに見つめていた色の補色を後の色に加色混合した色が見えます。
明度の点では始めに見つめた色と、後に見たの色の明暗の差がいっそう大きくなります。 |
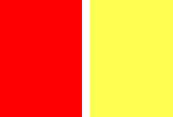 |
混色には、加色混色、中間混色、減法混色などがあります。
加色混色とは色光の混色の様に幾つかの色が混ざる事により元の色より明るくなる混色を言います。
(色付きのスポットライトの様に色光の3原色を混ぜると色が見えなります)
この場合の混色では 赤、黄、青(青紫)が基本色で、一定の条件下で混ぜ合わせた場合には他の色相を作り
出す事が可能になります。 赤と緑の混色の結果は黄色になり、緑と青の混色の結果はターコイズブルー(Cyan)
になり、赤と青の混色の結果は(Magennta)になります。
減法混色とは上記の混色とは反対に幾つかの色が混ざる事により元の色より暗くなる混色を言います。
(色のフィルターを重ねたり、絵の具の混色、印刷のインクの混色)
この場合の混色では 赤、黄、青、が基本色で一定の条件下で混ぜ合わせた場合にはみなさんがすでにペインティング
でミックスされている様な他の色相を作り出す事が可能になります。
中間混色とは元の色の中間の明るさになる混色を言います。
(点描、織物、カラーテレビ等の目で認識できないぐらい小さな色刺激を並べて色の混色)
この場合の視覚による混色では 赤、黄、緑、青 が基本色になり、混色結果は色相環で言うそれぞれの中間の色に
なります。 これらの基本色を総べて混ぜ合わせると灰色になります。
このページの概念とプレゼンテーション方法はヨハネスイッテンの本を参照しています。